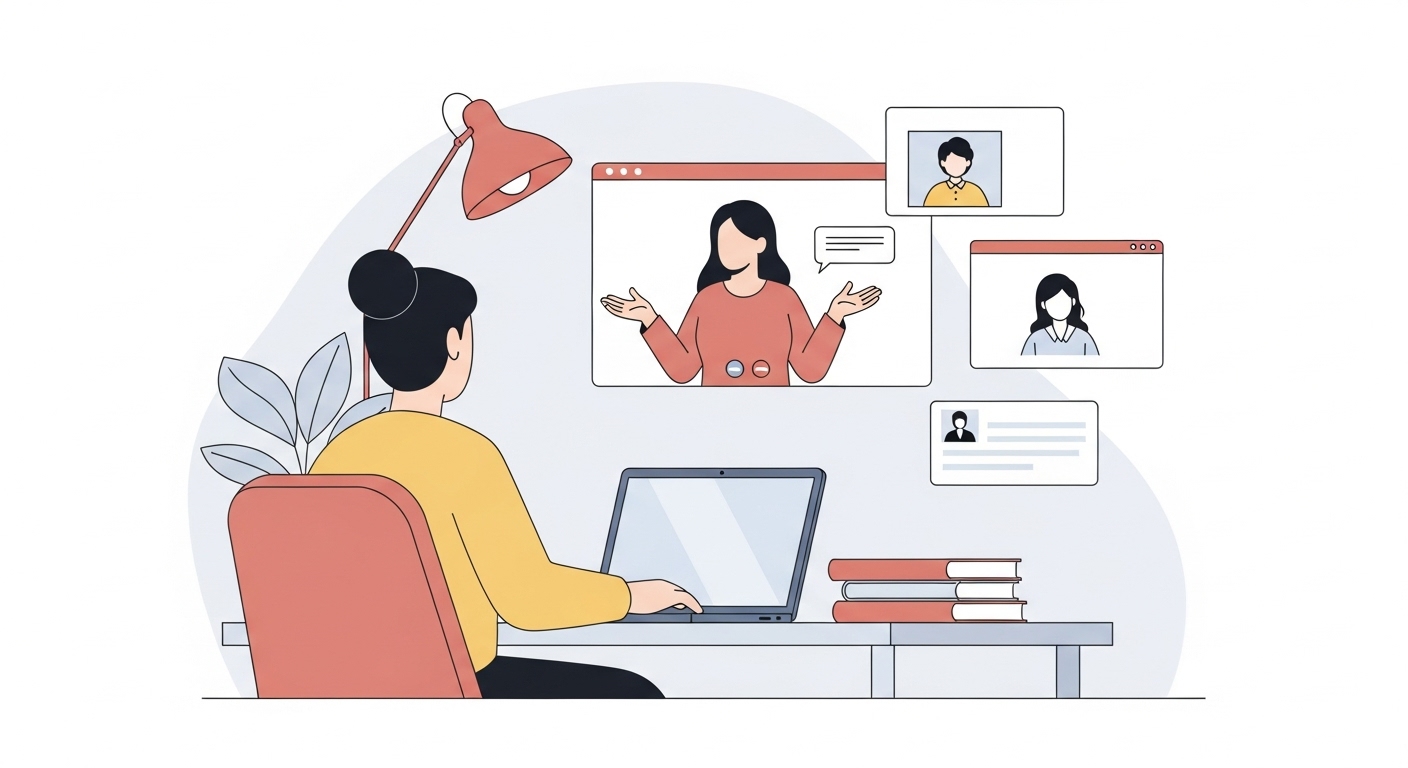料金当センターにご依頼頂いた場合の各種料金についてのご案内です。産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)費用と報酬許可区分法定費用(※1)行政書士報酬(税込み)新規申請81,000円110,000円更新申請73,000円88,000円変更許可申請71,000円99,000円変更届ー22,000円※上記金額は予告なく変更する場合がございます。(※1)ご自身で申請されても必要になる費用です。こちらは申請する自治体毎に必要となります。報酬額については役員2名以降から1名につき2,000円加算となります。運搬施設(車両等)が多い場合は別途加算対象となりますので、事前にお見積りいたします。複数の自治体へ申請がある場合は、事前にお見積りいたします。特別管理産業廃棄物を取り扱う場合は別途お見積りとなります。

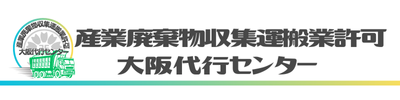






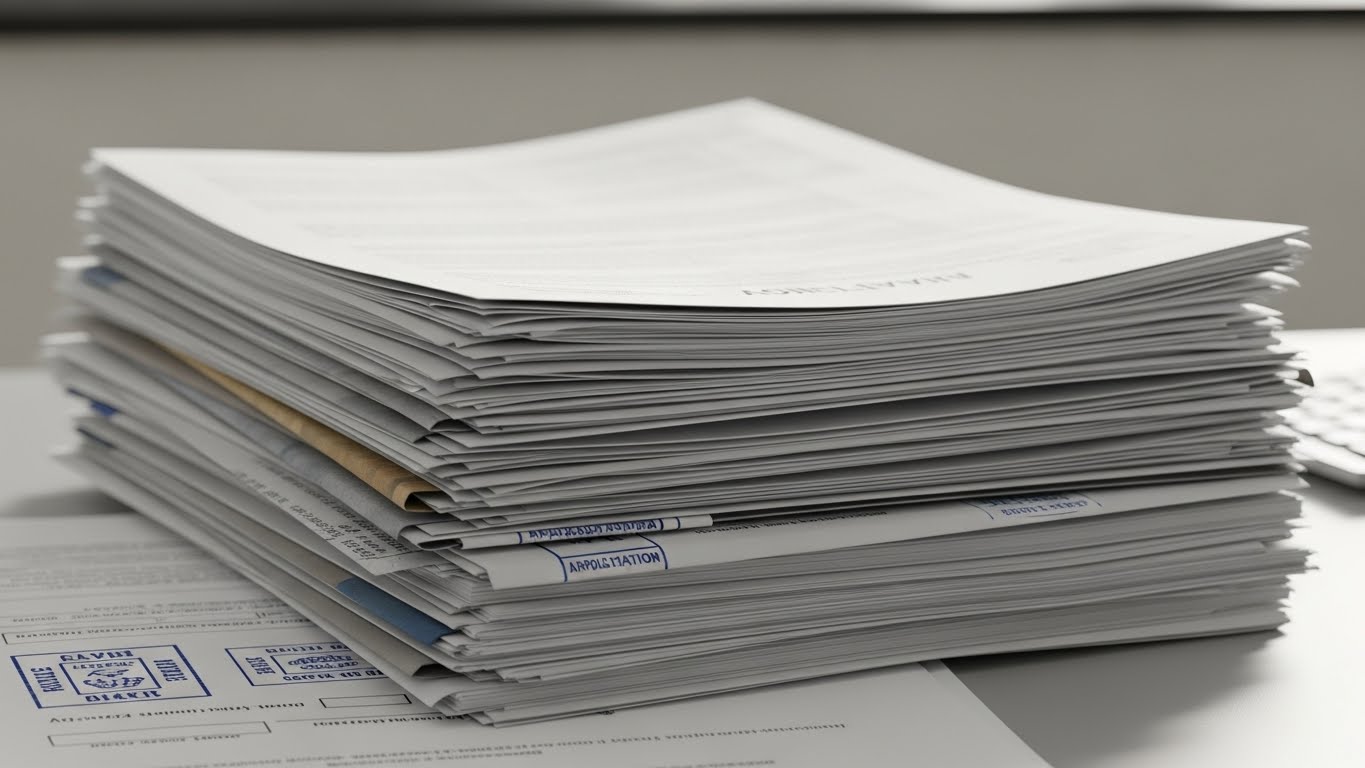
2.png)